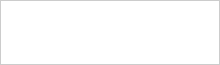第2回家庭教育講座
「読書感想文を楽しく書こう」
日時:2025年7月7日
講師:全国学校図書館協議会参与 對崎奈美子氏
ご参加いただいた保護者の方からいただいた感想を掲載します。
2年生保護者
■講演概要
今回の講演では、読書感想文を通じて子どもが単なる読書体験にとどまらず、「考える読書」を行い、一冊の本を通して自分の世界を広げていく意義についてお話を伺いました。
特に印象的だったのは、本の選び方についての指摘です。文字数や厚さなどの物理的条件ではなく、子どもが「他人に紹介したい」「面白いと感じた」と思える本を選ぶことが大切だという点でした。このような選書は、読書体験そのものの質を高める第一歩になると感じました。
また、小学校低学年における読書感想文の取り組み方についても具体的なお話がありました。長文を書くこと自体が難しい年齢であるため、親子一体となって取り組む必要があります。その際には、親が主導しすぎることなく、子どもの感性を活かしながら寄り添うことが大切であるという点も、非常に心に残りました。
■ワークショップ概要
講演後のワークショップでは、実際に感想文を書くための手法を体験する貴重な時間となりました。
・講師による読み聞かせ
課題図書:「出発:から草もようが行く」
※戦時下を生き延びた16歳の少年が主人公の物語
・感想の整理
読み聞かせ後、参加者は短冊6枚のうち5枚にそれぞれ簡潔なメッセージを記入しました。
・追加の読み聞かせと深掘り
その後、講師が「あとがき」を読み聞かせ、物語に関連する新聞記事や、実際の“から草模様”が描かれた風呂敷を提示。
これを受けて6枚目の短冊に、感じたことや新たな気づきを記入し、グループで共有しました。
この体験を通じて、感想文の準備段階において親が子どもに「問いかけ」や「導き」を行うことの重要性を実感しました。短冊形式は、文章の構成を整理する助けとなり、また関連資料に触れることで、より深みのある感想やメッセージが生まれることがわかりました。
■所感
私自身、今年わが子が初めて読書感想文に取り組むため、どのようにサポートすればよいか不安がありました。しかし今回の講演とワークショップを通じて、「親も一緒に考え、寄り添う姿勢」で臨むことの大切さを学びました。初めから「先導役」として意識を持つことで、親子ともにストレスなく取り組めるのではないかという前向きな気持ちになれました。
ただし、その子らしさを失わせてしまわないように、親が自分の価値観を押し付けないよう注意したいと感じています。子どもが自分自身の言葉で世界を広げることを、そっと支える立場でいたいと思いました。
また、今回体験した「短冊メソッド」は読書感想文だけに限らず、自由作文や意見文など、他の文章表現にも応用できると感じました。家庭でもぜひ取り入れていきたいと思います。
6年生保護者
本の選び方が重要だと改めて思いました。フィクションでも構わないと思うのですが、今回サンプル題材となったのはノンフィクションだったこと歴史的背景などを調べて描くことにもつながり、かつ文章はそこまで多いものではなく、絵本だったため、文章だけでなく絵からも想像をかきたてられるものでした。
その本の感想を書くことから、関連することに対して興味を持って調べて、その知識も含めて感想文に書いていくと、中身の濃いものになりそうだとかんじました。
ただし、小学生は(うちの子だけかもしれませんが)感想を聞くと字面だけよんで、「おもしろかった」「かなしかった」というだけのコメントしか浮かばないことが多く、そういったご家庭は、まずは親御さんが一緒になって感想を膨らませていくサポートをしてあげてください、とのことでした。
学校の授業でもよく新聞を作ったりすると思いますが、その際にもトピックをたくさん挙げて、それを見栄え良く整理して作り上げていく作業があるとおもいます。それと一緒で、今回のワークショップで実施した、付箋に感想を思いつく限りどんどん書いていって、それを整理してまとめていく作業で作り上げて行く方法は有効だなとおもいました。
5年生保護者
今回の講演で、講師による絵本の読み聞かせから感想を各々短冊に書き、4.5人のグループで共有することで、一冊の本に対しての感想をいろんな視点で知ることができた。
さらに同じ絵本を読み聞かせた講師のお孫さんの感想も共有してもらうことで、大人の視点と子供の視点でのこの本の感想の違いが興味深かった(大人は親目線から主人公を見ていたのに対し、子供は主人公の立場で見ていたこと、絵本の色彩が途中から変わっていたことへの気づきなど)。
今まで読書感想文を書くための本選びで、なるべく内容やページ数がが年齢に合っているものを選んできたが、子供本人が興味を持って読めるものなら絵本でもいいのだということが目からウロコだった。
一項目につき、1枚の短冊に感想を書いて、それを並べて文章の構成をしていくことで読書感想文が出来上がっていくこと、「面白かった」「怖かった」など一言で感想が終わってしまう子供には親が「どうしてそう思ったのか」など感想を広げるサポートをすると良いなど、具体的に読書感想文を書いていく過程を教えていただき、毎年苦労していた読書感想文が今年は少しスムーズに進められそうな気がします。
5年生保護者
聴講者の具体的な質問から講師の對崎先生が話された、生徒さん向けに実際に行っている「感想文の書き方ワークショップ」のお話がとても印象的でした。それ以外にも、実際に私たちもワークショップのさわり部分を体験したり、先生のお孫さんや小学生が実際に書いたという文章を紹介してくださいました。
改めて、文章をまとめることの難しさや、子どもへのサポートの重要性を感じました。
頂いた「読書感想文の描き方」のプリントは、サポートのイメージがしやすく、本当にありがたく思いました。まだまだ子育てが続く中での心強い味方となりそうです。
また、先生が「1年に一度くらいは一冊の本を通して世界を広げる、考える読書をしてほしい」と仰ったのが、子どもだけではなく親へのメッセージにも思え、心に残りました。
子どもと一緒に読書を楽しみ興味関心を広げる、そんな夏休みにしたいなと思える、そんな講座でした。