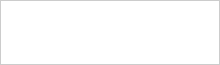第3回家庭教育講座
「親子で学ぶアンガーマネジメント」
日時:2025年8月1日
講師:日本アンガーマネジメント協会 小尻美奈氏、堀部三智子氏
ご参加いただいた保護者の方からいただいた感想を掲載します。
5年生保護者
キッズ向け講座と同時開催だったため、保護者たちと別会場で子どもたちも講座を受講した。
保護者向けの講座では、直近1週間でどんな風に叱ったことがあるか、その時の自分の状態などをペアワークで振り返った。子どもたちは年齢別に2グループにわかれて、自分の怒りの気持ちと上手に付き合うトレーニングを行った。
怒りは自然な感情だが、怒る必要のあることを上手に怒り、怒る必要のないことは怒らないようにすることがアンガーマネジメントと説明を受けた。
許せることと許せないことの境界線が曖昧では、自分の機嫌や状態で怒る・怒らないが変わり、怒りが相手に伝わらないため同じ行為を繰り返すことになる。
一定の基準で判断できるように境界線を固定する努力をしましょうと話があった。
印象深かったのは、悪い叱り方の例についてで、特に「何度も言ってるけど」は叱るときに言ってしまいがちな言葉だった。
しかし、この言葉を使うことで過去の出来事を思い出し、更に怒りが増して説教が長くなること、相手は怒られていることはわかっても「どうしたらいいのか」が伝わらないことを説明され、納得したと同時に使わないように気をつけたいと思った。
また、怒りがわいた衝動のままに叱ってしまうと感情的になるため、衝動から6秒間をやり過ごして冷静さを取り戻してから行動することが大切とのことだった。
衝動を抑えることはなかなか難しいが、怒りの対象から離れることは取り入れられそうなので、今後の生活で意識したいと思った。
4年生保護者
アンガーマネジメントはトレーニングであり、怒る時には以下の3つのルールを守ることで、年齢に関わらず誰でも行うことができるものだそうです。
①人を傷つけない(言葉でも、身体的にも)
②自分を傷つけない(ストレスによる暴飲暴食や、怒りを我慢することも含まれる)
③物を壊さない
この説明で特に驚いたのは、②の怒りを我慢しない事です。アンガーマネジメントは、怒ることを無くす、減らすトレーニングかと思っておりましたが、怒らなければいけない事を上手に怒るためのトレーニングでした。
怒りとは、防衛感情であり、自分の大切にしている『こうあるべき』という理想や願望を侵害されたと感じた時に発生するので、『〜べき』が多いほど怒る機会も増えてしまいます。
手放しても良い『〜べき』は手放し、まあまあ許せるという範囲を増やしていくことも必要だと感じました。
大切なのは、『まあまあ許せる』と『許せない』の境界線を、状況や感情によってあいまいにせず、いつでも同じ基準で怒ること、日頃から境界線を言葉で説明することであり、この境界線がブレると本当に怒りたいことが伝わりづらくなるとの事でしたので、実践していこうと思います。
2年生保護者
会場はシビックセンターで子供向けの口座も同時開催されていました。会場は親子別で分かれて入室します。講師の小尻先生は保育園などの教職を経た後、御自分の子育てで「怒り」に振り回されてしまうことからアンガーマネジメントに興味を持ったそうです。幼い娘と喧嘩をしてしまい、家出をした所、オートロックで家に入れなくなってしまったエピソードなど、自身の「怒り」によって困った経験を紹介して頂き、親しみやすく講義を聴くことができました。
アンガーマネジメントとは1970年代のアメリカで生まれた心理トレーニングで、決して怒らないことではなく、怒る必要がある時に、感情に振り回されずに適切に怒ることを目指した技術です。自尊心が傷ついたり、他者を傷つけるような行為に対してはしっかりと怒り、自分の中にあるマイナスの感情が引き起こす怒りは、爆発させるのではなく、深呼吸など心の余裕を確保した上で怒りの原因を注視し、許せるか怒るべきか理性的に判断するスキルを持つことが重要です。
怒りは誰もが持つ自然な感情で、自我を守る防衛的な機能を持った重要なもの。約束やルールを守る「べき」という価値観や道徳観が何度も無碍にされると、自分が蔑ろにされていると感じやすくなって何度も怒ってしまうが、その原因は自分が作り上げた「べき」というルールにもあるのではないか? そのルールが本当に必要な「べき」なのか見直すことも重要であり、それを「許す」ゾーンを少しづつ広げていくことも可能である。条件反射的に子供や家族に怒り散らし、「べき」を押し付けるのではなく、「べき」がなぜ必要なのか、自分が何故こうある「べき」と考えているのかを今一度家族と話し合い、個人個人の「べき」のすり合わせを行えば、怒りの連鎖を減らすことに繋がる筈。そう確信できる素晴らしい講座でした。