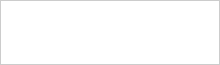第4回家庭教育講座
「保護者・学校・地域で考える ~子どもが求めるあなたのたった「一言」~」
日時:2025年9月18日
講師:暮らしとコミュニケーション研究所 親業訓練シニアインストラクター 今井真理子氏
ご参加いただいた保護者の方からいただいた感想を掲載します。
2年生保護者
アメリカの臨床心理学者トマス・ゴードン博士により1960年代に考案された、コミュニケーションの体験プログラム「親業」の方法に沿って、子どもと日頃接する心がけを学びました。
講師の丁寧な呼び掛けや、参加者同士のロールプレイもあり、色々な気付きを得られた学びの時間となりました。
親は、子どもに何か困りごとがあった時、自分の先入観や親切心でつい「こうしたら?」「そんなこと言わないの!」などの声かけをついしてしまいます。
まずは、
①「そういうことで困ってるんだね」と受容し、
②相手がどんな気持ちか理解しようという気持ちで、相槌をうちながら聞き、
③子どもの気持ちを確認する
というプロセスで、子どもと向き合うことが大切、と教わりました。
聞く時に、親の意見は挟まない、解決策を提案しないのはこちらに覚悟がないとできないなと感じました。
子どもを信じて、否定せずに寄り添う、という考えはよく聞くのですが、意識しないと簡単に忘れてしまいます。
こうして、聞くことの心構えをあらためてうかがうことで、普段のやり取りこそ大切だということを実感しました。
3年生保護者
トマス・ゴードン博士によって考案されたゴードンメソッドに基づく3つ基本的な方法、聞くとき、伝えるとき、対立の解き方、について講師の解説やロールプレイングを通して学びました。 子供の困りごと、苛立ちなどを聞くときは、相槌を打つが同意も否定もせず、相手の話を黙って最後まで聞く、相手の気持ちを分かろうとする聞き方が大切だそうです。 つい子供に解決策を提示したり、小言を言ってしまいますが、それをせず、問題の解決は子供に委ねていいと学ぶことができました。 頭では理解できても、その場になったとき、その瞬間にその対応が取れるようになるためには、しっかり自分の中での意識、努力することが必要になるなと思います。 また、伝えるときも相手の行動に対しては言及せず、こちら側、自分が何を心配して、どうして困るのかだけを伝えることが、子供に対して聞いてもらえる声かけであると知ることができました。 2時間という短い時間の中でなかなか深く理解することは難しかったですが、自分の普段の声かけが良い親子関係を築いていくうえで大切か、改めて学ぶことが出来ました。
3年生保護者
ゴードンメソッドの3つの基本的な方法について学びました。
まずゴードンメソッドとは、アメリカの臨床心理学者トマス・ゴードン博士によって考案されたコミュニケーショントレーニングのプログラムです。その中で親子関係を豊かに温かく健全なものにし、子どもの健やかな成長を実現するため親たちに一つの方向性を示したものが「親業」です。
メソッドには、1聞くとき、2伝える時、3対立の解き方、の3つの基本的な方法があり、例をあげながらの先生のお話に引き込まれました。
その中の「コミュニケーションを阻む可能性のあるお決まりの12の型」というものにハッとさせられました。
①命令、②脅迫、③説教、④提案、⑤講義、⑥非難、⑦同意、⑧侮辱、
⑨分析、⑩激励、⑪質問、⑫ごまかし
これらは、子どもが悩んだり困ったりしている時に親がやりがちな対応で、これらの意見を言うことは、親が話しの主導権を握り、子どもが話す機会や自ら考え解決する機会を奪ってしまっている、ということです。
この場合、まず子どもの感情のガス抜きをして(そうなんだね、困っているんだね、など自分の意志を反映しない返事をする、あいづちをうつ)、子どもの反応をみる。そして問題の解決を子どもにゆだねる。その力を身につけることが自己肯定感を高めることにもつながっていくとのことでした。
今日からでも始められる、とおっしゃっていただいたので、子どもが帰宅後、実践できそうなシチュエーションになったため試してみることに。
息子「今日はやる気がないなぁ、、」←宿題のこと
私「やる気がないんだね、、」
息子「少し気分転換したらやる気が出るかな、、」
私「そうかもしれないね、、」
息子は楽しいことに熱中しはじめました。いつもならこの辺でイラッとしはじめ、まだやらないの?など声をかけますが、ガマンガマン。
私「◯時にはお風呂に入るよ」とだけ伝えて家事をしていました。
しばらくすると私のところへきて、
息子「やっぱりやる気にならない、、」
私「やる気にならないんだね、、」
を何度かくりかえし、学校で何かあったのかもと思い、
私「何かあったの?」と聞いてみると息子はやる気にならない理由を考え始め、最後に「ママだったらどうする?どうすればいい?」と聞いてきました。
いつもならこのやりとりの間に
お決まりの12の型のどれかで返していてお互い険悪になったと思います。
私「ママだってやる気がない時はあるけど、今はゴハンを作ったり家事をすることがママのやるべきことだからやっているよ」と言うとだまってリビングへ。用事をすませリビングをのぞくと宿題を始めていました。先ほどとは違い落ち着いていることにも驚きました。 相手の話を聞き、相手に意見するのではなく、自分のことを伝える、大切なことだな、と実感しました。
今回の講義はメソッドのほんの一部だと思いますが、それに触れ、もう少し深く学びたいと思いました。
4年生保護者
臨床心理学者トマス・ゴードン博士の考案した「親業」を元にロールプレイを交えながら子どもとのコミュニケーション術を学びました。
ロールプレイは二人一組で行いました。まず最初に2パターンの挨拶をしました。
パターン1は
B「Bです」
A「Aです」
と名前のみ
パターン2は
B「Bです」
A「Bさんですね。Aです」
と相手の名前の確認後、名乗る
先に名乗った時、パターン2の方が、話を聞いてもらえ、伝わっているという感じがありました。
相手が確認したことの効果だそうです。
その後もいくつかのロールプレイで、「12の型」の入った声掛けと相手の話、気持ちを理解しようとし、自分の理解したことを確認する声掛けの二種類を試しました。
後者は、肯定も否定もないのになぜだか、「そうなの。それでね」と話を続けたくなる感じがしました。
言葉でうまく説明できない感情の機微なのですが、親業の真意としているものを感じることが出来たと思います。
親業を用いることで子どもが自分で困り事と向き合い考える力がつく、自己肯定感が上がる、親子関係が良くなるなど様々な効果があるようです。
そうはいわれても我が子は考える力があるか不安だと言う意見が受講者から出ていました。
子どもは元々考える力があったけれど、解決策を示されたり、ダメ出しをされることで考えることを止め、受け身になってしまって、評価される事を選ぶ。とおっしゃっていました。
口を開ければ「12の型」はスラスラと出てきてしまいます。
親業を意識して子どもに、「自分は親に理解されている」という感情を育て、まずは自分で考える習慣をつけられればと思いました。
12の型(12のロードブロック)とは、コミュニケーションを阻む可能性のある誰でもする、命令 、脅迫、説教、提案、講義、非難、同意、辱しめる、分析、同情、尋問、ごまかす という行為。
親が子どもに対してやりがち。子どもが黙ったり反抗したりイライラしたり、自分はダメだと思ってしまう。