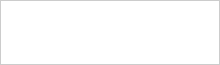第6回家庭教育講座
「発達障害の「いま」と「これから」」
日時:2025年11月6日
講師:東京都発達障害者支援センター相談支援員 柏木理江氏
ご参加いただいた保護者の方からいただいた感想を掲載します。
4年生保護者
11月6日、『発達障害の「いま」と「これから」』について、お話を伺いました。
去年も同様の講座があり、内容はほぼ同様とのことでした。発達障害の定義や特徴などについてのご説明と、対処法についてのお話がありました。本当にさまざまな症例があることと、暮らしやすくなるための対処方法を数多くご紹介いただき、環境・道具・方法の変更など、大変参考になりました。
質疑応答では、現在発達障害をお持ちのお子様のお母さん方から、現実的なご質問が寄せられ、丁寧に答えられていました。
6年生保護者
障害と言う言葉で表されているが、生まれながらの特徴、脳の働き方で通常とは違う特徴が出る、障害は無くならないが、年齢を重ねたり、周りの人の関わり方で変わって(成長)していくのが発達障害の定義としてお話しされました。
発達障害と言う言葉は浸透しているが、正しく理解されていない面もあり、誤解される事も多いそうです。
限局性学習症や注意欠如/多動症、自閉スペクトラム症など、様々な種類の障害があり、それぞれの特徴や関わり方について、長年の経験から実際の事例を交えてお話しされました。
特に強調していたのは、根本的な苦手を変えるよりも、環境、方法、道具の変更をする事が良いこと、試行錯誤していく過程が大事と言うことでした。
貴重な講演に参加させて頂き、ありがとうございました。
3年生保護者
こどもTOSCA相談支援員、柏木講師のお話をうかがいました。
発達障害の定義は、生まれながら脳の「働き方」に通常とは違う特徴が現れ、ものごとの理解の仕方や社会性の発達などに影響が出る、障害はなくならないが年齢を重ねたり周りの人のかかわり方変わって(成長して)いく、ということでした。
特徴は大きく分けて3つあり、
◯限局性学習症 LD→読む、書く、計算などの「学習的技能」が困難で、できること、できないことにアンバランスが生じる。
◯注意欠如・多動症 AD/HD→不注意、多動性、衝動性の特徴への課題がある。
◯自閉スペクトラム症→社会性や対人関係に関わる課題がある。
これらの障害について正しく理解されず、誤解や行き違いが生じてしまう場合があるとのことでした。
誰かに相談をすることや、手を借りた結果、事態が好転する、など「状況が変化していく」実体験が貴重で、子どもの場合、親が指示するのではなく一緒に考え試行錯誤を繰り返すことが大切とのお話でした。
ご自身の体験や実例を交えたお話、最後の質疑応答など、貴重なお話をうかがうことができました。
5年生保護者
発達障害には限定性学習症 LD、注意欠陥多動性障害 AD/HD、自閉スペクトラム症 ASDの3つがあり、これらが重なり合うこともあるそうです。
障害はなくなることはないが、年齢を重ねたり、周りの人の関わり方で、変わっていくとのことです。
一つのことをするのにものすごくつかれてしまう、周りから不真面目にみられてしまうなど生活するうえで苦労が多く、その暮らしやすさを上げるために、自分の特性を踏まえた上で自分に合った方法を探しやってみることが大事で、実体験、トライ&エラー、微調整を繰り返すことがよいとのことでした。
講師の方が実際に相談されたり経験された具体例を話されており、より理解が深まりました。
4年生保護者
参加者が多く、発達障害への関心の高さが伺えました。
困り事をなくす努力は労力のわりに成果が出にくいので、そこは諦め、困り事が起こったときにどう対処するか、自分に合った対処法を見つけておくことで、暮らしやすくなるという話しが印象的でした。
生まれながらの脳の特徴だからこそ、うまく付き合える方法を見つけ、こころ穏やかに過ごせればと思いました。
講師の方を通してですが当事者の感じ方が、聞けてよかったです。
6年生保護者
柏木理江講師による発達障害の「いま」と「これから」に参加いたしました。
これまで、発達障害という言葉はよく耳にしていたものの、あまり深く考えることはありませんでした。今回参加してみて、特徴は大きく分けると3つあり、それぞれの内容が全く違うということをとてもわかりやすく学べた機会でした。ありがとうございました。